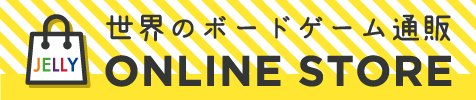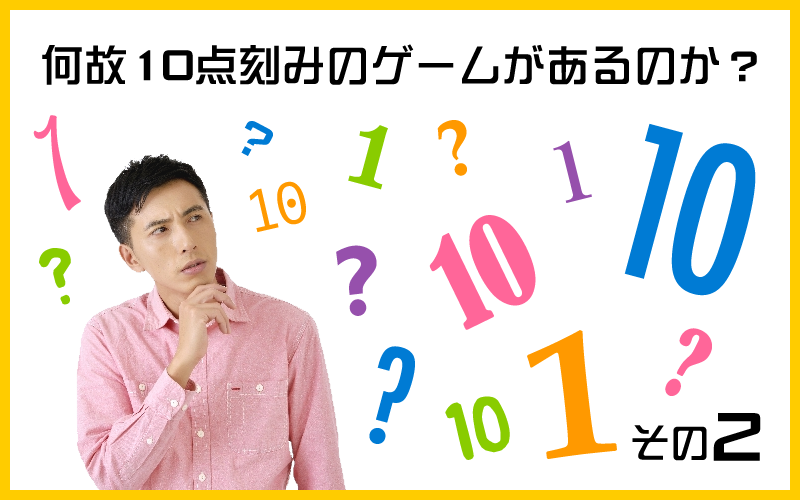
今回も何故最小単位が大きいゲームがあるのかについての理由の続きです。
前回とは違い今回は、普段得点として得ている数字について考えてみました。
2認識しやすさ、意識している、使い慣れている満足感
普段あんまり、得点、褒章で1や2という単位を使うことがないなあと思います。
どういうことかというと、日常生活で意識している数字で多いのは100分率なんじゃないかと最近思っています。
学校のテストや、進捗具合といった際にはパーセンテージで把握や管理をしているひとが多いのではないでしょうか?
テストで10点満点のテストを受ける人は大人になるほどあまりいないのではないでしょうか?
そうすると100点満点のテストを受けることのほうが遥かに多いはずです。
その際に1点上がっても対して変わらないと思いますが、10点は明確な差として感じるのではないでしょうか。
それに慣れているため、ゲームでも1点が最小単位の時よりも1点と2点の間に感じる得点差よりも、10点が最小の時の10点と20点の方が差としての意味は一緒のはずなんですが、差を感じる、満足感を得られたりするのではないでしょうか?
また、普段から使っている数といえばお金がありますが、こちらもあまり1円、2円を気にしている人は大人になるほど少ないような気がします。もちろん1円2円を意識するのは大事なことですが。
認識している最小単位が日常だと大きいためにゲームでもそう感じられるように、そういう満足感が得られるために最小得点単位が高く設定されているんじゃないのでしょうか?
事実、確かにお金をテーマにしたゲームは得点の最小単位が大きい事が多いです。(ダイレクトにお金が得点なので当然といえば当然ですが。)
そんな感じで、今回はゲームから脱線して考えて、普段意識している数字、褒章である点数やお金が大きいから、大きい数のゲームもあるんじゃないかという考えでした。
そんなこんなでなんとその3に続く。
 最寄りのJELLY JELLY CAFEを調べる
最寄りのJELLY JELLY CAFEを調べる
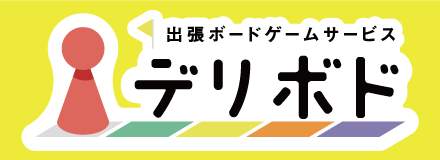


 SHARE
SHARE